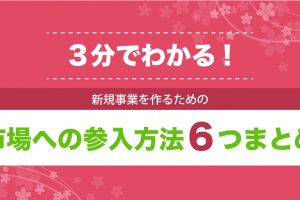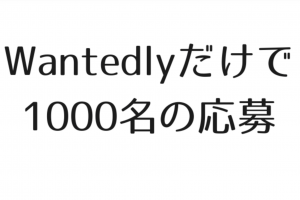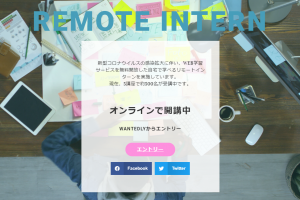みなさま、ごきげんよう。ディップの安元一耀です。
サムネイル画像がYoutuberみたいになりましたが気にせず記事を書いていきます。
僕はディップで新規事業を企画する職種でして、現在は福利厚生領域の事業を検討しています(検討というか、もうやるつもりでいます)
事業を考える時、僕は必ず競合をリサーチします。なので今回は、福利厚生市場でシェアNo.1のベネフィット・ワンについてリサーチした結果を記事にします。
ベネフィット・ワンが提供している「ベネフィット・ステーション」というサービスを見ると、ホテルが80% OFFとか、とんでもない割引率の商品がたくさんあります。
今回は、「なぜそんな割引率が実現できているのか?」に加えて、「ベネフィット・ワンが展開している事業詳細」について書いていきます。
[toc]ベネフィット・ワンが展開している7つの事業
ベネフィット・ワンの決算資料を読んでみると、以下の記載がありました。
決算短信には、各事業ごとの売上や営利などが記載されています。

(参照:ベネフィット・ワン 2020年決算短信)
これだけではさすがに事業詳細がわからないので、ここからは、自分なりに調べた事業詳細について書いていきます。
1:福利厚生事業(通期売上=約170億円)
ベネフィット・ワンの一番の主力事業である「ベネフィット・ステーション」のことです。内容は、企業への福利厚生代行サービスです。
企業がベネフィット・ワンに入会金と月額費を支払うことで、その企業の従業員は飲食店やレジャー施設などを割引で使えるようになります。
特徴としては大企業への導入に強く、東証1部上場企業におけるシェア=46.5%とのこと。官公庁や地方自治への導入にも強く、官公庁におけるシェアは約50%らしいです。
上記の仕組みは多くの人が知っていると思うのですが、ベネフィット・ワンの福利厚生事業をもっと細かくリサーチしてみると、以下の「①補助金」と「②送客手数料」という仕組みがあることがわかりました。

①:補助金
ベネフィット・ステーションのメニューを見てみると、ホテル宿泊80% offなど、物凄い割引率のメニューがたまにあります。
以下の画像は、とあるダイビングクラブが提供している「オーシャンダイバー」という資格の取得コースらしいのですが、通常価格102,300円が21,780円にまで割引されてます(約80% OFF)

(参照:https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/srch/menuPrticSrchRslt.faces?menuNo=622468)
このダイビングクラブの割引許容額はわかりませんが、仮に102,300円から30% OFFの71,610円を割引許容額としてみます。
すると、今回は約80% OFFの21,780円でサービを提供しているので、71,610円ー21,780円=49,830円も割引許容額をオーバーしています。
じゃ、この49,830円は誰が負担しているのか?という話ですが、これはベネフィット・ワンが福利厚生メニュー提供企業への補助金という名目で支払っています。
補助金の原資はどこから来ているのか?
じゃ、その補助金の原資はどこから来ているのか?という話ですが、これはベネフィット・ステーションの加入企業が毎月ベネフィット・ワンに支払っている月会費がメインとなっているはずです。
つまり、ベネフィット・ステーションの利用者が増えれば増えるほど補助金は増大し、ベネフィット・ワンの粗利率は低下するというジレンマの事業構造があると思います。
②:送客手数料
その補助金のジレンマの構造を緩和するためか、ベネフィット・ワンは一部の福利厚生メニュー提供企業からの送客手数料を成果報酬で受け取っています。
ベネフィット・ワンは、顧客(企業)数を増やしてベネフィット・ステーションの加入者を増加させることで、福利厚生メニュー提供企業への価格交渉力を強めることができます。すると、補助金の支払額も下がっていくはずです。
2:パーソナル事業(通期売上=約25億円)
これは一言で言うと、ベネフィット・ワンの代理店のようなものであると個人的には認識しています。
ベネフィット・ワンのIR情報によると、以下の説明がありました。

(参照:https://bs.benefit-one.co.jp/BE-ONE/IR/pressrelease/pdf/2010/pr20101108.pdf)
つまり、多くの消費者を顧客として抱えている会社(上記画像で言うと協業会社)、例えば、携帯販売会社とか不動産とか。
が、消費者に商品(携帯販売会社なら携帯、不動産なら物件)と一緒にベネフィット・ステーションへの加入も勧めるわけです。
で、消費者は毎月ベネフィット・ステーションの月会費を支払うので、その会費を協業会社とベネフィット・ワンでレベニューシェアするという構造です。
個人でベネフィット・ステーションに加入する場合の月会費は300円ほどですが、それで売上25億円も出せているのが凄すぎだと思います。。。
3:CRM事業(通期売上=約5億円)
CRM事業はパーソナル事業とかなり似ていますが、ビジネスモデルに少しだけ違いがあります。
パーソナル事業では、ベネフィット・ステーションの月会費は協業会社の顧客(消費者)が負担しますが、CRM事業では、協業会社が月会費を全額負担します。

ベネフィット・ワンのホームページを見てみると、
消費者側では、生活の質的な豊かさを追求する成熟した社会の到来と価値観の多様化や高齢化の進展などを背景に、より価値の高いサービスのニーズが高まり、企業側では、優良顧客セグメントの囲い込みのツールとして、高付加価値会員サービスの需要がいっそう増すと予測されます。
と記載されています。つまり、「協業企業のマーケツールとしてベネフィット・ステーションを使ってください」ということなのでしょう。
4:インセンティブ事業(通期売上=約37億円)
営業マンには、「インセンティブ」という報酬体系があったりします。月の営業目標数値を上回ったら、その分だけ多く給与が貰えるみたいな制度です。
その給与を、お金ではなくポイント(1ポイント=1円)で付与する仕組みを提供しているのがインセンティブ事業となります。

(参照:https://bs.benefit-one.co.jp/incentivepoint/system.html)
料金は、以下の仕組みになっていました(システム導入費用=30万円…)
5:ヘルスケア事業(通期売上=約100億円)
企業や医療保険者に対して、「健康診断の予約 / 精算代行サービス」「特定保健指導代行サービス」を提供しています。
全国の健診機関との契約〜従業員への告知・日時予約・精算事務・健診結果の告知など、健康診断に関わる業務をワンストップで代行するサービスです。
調べてみると、ベネフィット・ワン以外の福利厚生サービス提供事業者(イーウェル / リロクラブ)もヘルスケア領域への参入が見られました。
ベネフィット・ワンによると、福利厚生サービス提供事業者がヘルスケア領域に参入する理由として、主に以下の2つを挙げていました。
1:健康経営に対する関心の高まり
2015年より始まった従業員のストレスチェック制度義務化など、従業員の健康問題が重要視され始めました。
健康診断やストレスチェックなどは福利厚生と同じく、人事の業務領域です。よって、福利厚生サービス提供事業者は、福利厚生に加えてヘルスケアのサービスも一緒に提供することで、ワンストップでの人事業務支援を狙うことが可能になります。
2:人事DBの活用
福利厚生もヘルスケアサービスも、共に人事のDBを活用します。
情報漏洩などのリスク観点から、そのDBにアクセスできる企業は少ない方が良いと考える企業が多いため、福利厚生サービス提供事業者がヘルスケアのサービスを提供することに優位性があるとしています。
6:購買・精算代行事業(通期売上=約7.5億円)
ベネフィット・ワンの決算資料ではこの事業についてあまり触れられてはいませんでしたが、以下の資料に少し記載がありました。
「Hi-VOXサービス」「出張ステーション NEXT」「接待ステーション」というサービスを展開しているとのことでした。
Hi-VOXサービス
これは企業の小口精算業務のBPOです。以下の資料を見つけました。

(参照:https://corp.benefit-one.co.jp/images/service/solutions.pdf)
出張ステーション NEXT
わかりやすいネーミングです。企業の出張手配・精算業務をシステムで集中購買・管理するBPOサービスです。
企業が本サービスを使用するメリットとして、以下の3つを挙げています。1つ目に記載されてある、「法人契約の特別割引料金」ってあるんですね。。。
接待ステーション
これもわかりやすいネーミングです。接待に必要な店の予約〜精算業務を代行するのBPOサービスです。
以下の資料によると、お店(飲食店)からは送客手数料として10%をベネフィット・ワンがもらっているとのことです。

(参照:https://corp.benefit-one.co.jp/service/supplier/reception/entry/)
飲食店の平均的な営業利益率を考慮すると、送客手数料10%ってかなり強気な数値だなという印象です。
7:海外事業(通期売上=約8.5億円)
こちらは以下の資料に「主としてインセンティブ事業を展開。」と記載がありましたので、詳細は割愛です。
以上がベネフィット・ワンが展開している7つの事業となります。
ベネフィット・ワンの成長戦略としては、福利厚生から始まり、ヘルスケア・出張代行・小口精算代行などで人事データを徹底的に刈り取り、そのデータを元にレコメンドを実現すると記載があります。
レコメンドの詳細については特に触れていませんでした。
個人的感想:ベネフィット・ワンはスイッチングコストを上げるための施策を徹底している
これは個人的な意見ですが、ベネフィット・ワンは企業のスイッチングコストを上げるための施策が優れていると感じます。
スイッチングコストを上げるための定石施策として挙げられる、以下の3つを実施しているからです。
1:業務の重要部分に関わる・深くまで関わる
AWS / BPOサービスなどが例として挙げられます。
AWSから他のサーバーに乗り換えようとすると、企業にとってはサービスの一時停止・他部署の巻き込み業務などが発生してしまうため、心理的ハードルが上がります。なので、業務の重要部分に関わるというのはスイッチングコストを上げるために有効な施策です。
ベネフィット・ワンが代行している小口精算や出張代行などは、企業の業務を理解しないと回りません。企業はベネフィット・ワンに業務回りの整理・共有を行いますが、これをベネフィット・ワン以外のBPO会社にもう一度説明するのはかなり面倒なはずです。
2:データを蓄積する
これはSanSanなどがわかりやすいかと思います。データを蓄積することで、そのデータ自体が価値になる場合、スイッチングコストは当然上がります。
※実際に、SanSanのチャーンレートが1%を切っています。
ベネフィット・ワンも、決算発表で「レコメンド」を強調しているのはそのためではないか?と推測しています。
3:ポイントなどによる囲い込み
これは楽天ポイントや航空会社のマイルなどが例として挙げられます。消費者は「楽天ポイントが使えるから」という理由で楽天経済圏から離れにくくなります。
ベネフィット・ワンが提供していているポイントシステムもこれを狙っているはずです。
というわけで今回はこれで終了です、ありがとうございました。
メンバー募集中!
ディップでは、一緒に働くメンバーを募集しています。
ご興味がある方、ぜひカジュアルにお話しませんか?下記リンクより、ご連絡お待ちしております。
Wantedlyのアカウントをお持ちでない方
[blogcard url=”https://form.run/@openentry”]Wantedlyのアカウントをお持ちの方はこちらからの方がスムーズです!